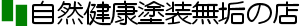サンウッド旧ニュース6
元加賀小、シックハウスで廃校へ避難
東京江東区 (2003.5.6 読売)
>>ヘッドライン
基準値を上回る濃度のトルエン
東京・江東区立元加賀小学校で、耐震改修工事後の校舎の一部から、国の基準値を 上回る濃度のトルエンが検出されていたことが分かり、同区教委は6日、1―3年生 と障害児学級の児童計約180人を、昨年廃校になった近くの旧区立白河小に移した。 4―6年生については先月30日から同小で授業を行っており、全校児童約350人 が丸ごと“避難”する異例の事態となった。
区教委では、校舎内の換気や吸着剤によるトルエンの除去を続けるが、少なくとも 夏休みまでは旧区立白河小で授業を行う見通し。
元加賀小の耐震改修工事は、昨年8月から今年3月にかけて実施され、内壁の塗り 替えなどが行われた。先月20日、区教委の依頼で東京都環境科学研究所が、シック ハウス症候群の原因物質とされるトルエンなど有害物質を測定し、基準値以上のトル エンが検出された。児童からは目がちかちかするなどの訴えがあったという。
シックハウス症候群は、住宅建材などから出る化学物質を吸い込んだ際に起きる頭 痛や吐き気などの症状。新校舎を巡っては、東京都調布市立調和小でも、児童10人 が転校したり不登校児施設に避難したりする“被害”が出たほか、長野県塩尻市立塩 尻西小、東京都墨田区立八広小でも同症候群の疑いが明らかになっている。
調布市でも「シックスクール」
東京調布市 (2003.5.4 読売)
>>ヘッドライン
木のぬくもり目指したはずが
木のぬくもりが満ちた学校に、我が子を通わせたいと思う親は多いだろう。だが、 心を癒やすはずの校舎でシックハウス症候群にかかるとしたら……。国も推奨する “木造”校舎のブームに乗り、予期せぬ「シックスクール」の悲劇を呼び込んだ学校 が、東京都調布市にある。
■先端設計■
皮膚科医の笹川征雄さん(59)が副理事長を務める大阪のNPO「シックハウス を考える会」に、調布市教育委員会から電話がかかったのは、昨年10月下旬のこと だった。
完成したばかりの同市立調和小学校(児童398人)の新校舎でシックハウス症候 群が発生した疑いがあり、調査を委託したいという。「行政がNPOを頼るとは。追 い詰められたんやな」。すぐに検診のため調和小を訪ねた。そして驚いた。
円筒形のラウンジから翼を広げるように延びるフローリングの廊下、複雑な配置で 並ぶ部屋。従来の校舎のデザインとまるで違う。
冷暖房も完備。なのに、初秋の寒さが身にしみた。化学物質対策で窓を開け放して いるのだ。診察を待つ上半身裸の子供たち――。
■誤算■
予兆はあった。昨年8月28日、校舎を建てた大手ゼネコンが市教委に出した報告 書は、約10日前の空気測定で有害なトルエンの濃度が国の指針値の最大約15倍に 達し、ホルムアルデヒドも2か所で指針値を超えたとしていた。
それでも5日後に予定通り授業を始めた。昨春、指針値オーバーの校舎の使用を禁 じる国の新基準ができたが、調和小の工事契約は一昨年春で対象外。ゼネコン側は 「(指針値を守る)義務はなかった」と主張する。市教委も「最も化学物質放散量が 少ない建材を使った。授業開始までに換気すれば大丈夫」と考えた。
教室では冷房のため窓を閉めた。ある姉妹が目を真っ赤にして帰宅し、鼻血を大量 に出したのは9月半ば。母親(43)は「水泳の授業のせいかな」と思った。頭痛や 疲労感を訴える児童も出たが、病院は「通常のアレルギー」「原因不明」などと診断 した。
報告書が初めて公表されたのは、10月11日の保護者説明会。騒ぎは大きくなり、 姉妹を含む10人が転校したり不登校児施設に避難したりした。笹川さんの検診結果 は、「全児童の2割が化学物質の影響を受けた可能性が高い」。同市は今年2月、教 育部長ら5人を減給などの処分にした。
■落とし穴■
「考える会」の白瀬哲夫さん(52)は3月末、建材メーカー社員の立場から調査 結果をまとめた。フローリングの教室が特に高濃度で、接着剤を多用する合板がホル ムアルデヒドとトルエンを含んでいた。「合板の内装」と「冷暖房効率の良い高気密 の鉄筋コンクリート造」。化学物質が室内にこもる組み合わせに、落とし穴があった。
高度経済成長期、一直線の廊下沿いに教室を並べた「片廊下横一文字方式」の、没 個性のビニール床校舎が量産された。その反省から、旧文部省は1986年、木を活 用した校舎に建築費助成を始め、今では新・改築校舎の90%以上が助成を受ける。 しかし純粋な木造は6%で、大半は床や壁に合板などを張るだけ。最近シックスクー ルと断定された塩尻西小(長野県塩尻市)や湊保育園(大阪府堺市)なども同じ構造 だ。
しかも調和小では、デザイン優先の大きな窓が転落防止のため幅15センチしか開 かなかった。配置も偏り、風通しが悪い。
白瀬さんは言う。「昔の校舎は殺風景でも風は通った。木のぬくもりは大切だが、 天然木を使うなど本当の意味で自然志向にしないとだめなのです」
健康被害は1か月で収まったが、転校・避難児童のうち5人は他校で新学年を迎え た。夏が近づき、日差しで再び化学物質が放散する懸念が消えないからだ。先月29 日、調和小では窓を全開できるよう改良した。ただ建材の化学物質が完全に消えるま でには時間がかかる。それがいつなのか、誰にもわからない。
東京では先月、江東区立元加賀小と墨田区立八広小でもシックハウス症候群の疑い が発覚し、元加賀小は、全校児童を別の校舎へ避難させることを決めた。
シックスクールの恐怖は、広がる。
◆シックハウス症候群=住宅建材などから放散される化学物質を吸い込むと起きる、 頭痛や吐き気などの症状。アレルギー患者が発症しやすく、進行すると微量でも重症 に陥る。正式な病名がないため、最近まで国の対策が遅れていた。
小学校で基準超すトルエン
東京江東区 (2003.5.1 共同)
>>ヘッドライン
元加賀小学校一時移転
東京都江東区の区立元加賀小学校(児童351人)で、シッ クハウス症候群の原因とされる化学物質トルエンが、国の基準値を 超えて検出されていたことが一日、分かった。
目やのどの痛みを訴える児童が続出。アレルギー症状がある3人 が転校するなどの被害が出たことから、区教委は濃度が下がるまで の1―2カ月間、全児童を廃校になっている近くの別の小学校に移 すことを決めた。
区教委によると、同校では昨年8月から全校舎の改修工事を実施 。終了後の3月中旬に都の検査機関が行った調査で、最高で国の指 針値(○・○7PPM)の7.5倍に上るトルエンを検出した。し かし、区が民間の機関に委託して再調査した結果、校長室以外は指 針値以下だったため、4月から通常通りの授業を始めた。
その後、児童からの被害の訴えを受けて4月20日、都の別の機 関が3度目の測定をした際、教室で最高で3.6倍の値を検出した という。
区教委は「区の検査で一度は問題ないと判断したが、結果的に被 害が出たので移転を決めた。3回の結果が異なる原因は、当日の気 象条件の違いなどが考えられるが、詳しくは分からない」としてい る。
都心の小中生シックハウス疑い1・7%
厚労相 (2003.4.27 共同)
>>ヘッドライン
新潟のケースの約二倍
東京都心部の小中学生の約1・7%にシックハウス症候群の疑い があり、比較対照した新潟のケースの約二倍に達するとの調査結果 を27日、東京慈恵会医科大、昭和大のグループが福岡市であっ た日本小児科学会で発表した。疫学調査は厚労省の研究班として実 施された。
グループは昨年2月、東京都港区のほぼすべての公立小、中学校 の児童・生徒約7,000人と保護者にアンケートを送付。回答のあった 約3,500人について検討した。ことし2月には新潟県津南町でも 同様に実施、約900人から回答を得た。
港区では、住宅の新・改築後、 においに伴い頭痛や目がチカチカするなどの症状が出たり、 もともとあった症状が悪化する「シック ハウス症候群疑い例」に該当した児童・生徒が61人(約1・7 %)に上った。
家族にも同様の症状がある「症候群疑い濃厚例」は11人(約0 ・3%)。津南町では疑い例が約0・8%と低かった。
原因物質として、壁や床のにおいを挙げる回答が多く、症状のあ る家庭の約70%で、過去5年以内に新、改築が行われていた。
疑い例には高い頻度でアレルギー症状もみられた。港区では、ア レルギー性鼻炎のある児童・生徒が全体では約22%なのに対し、 疑い例では約54%。アトピー性皮膚炎も全体の約18%に対し疑 い例は約38%と高率だった。
東京慈恵会医科大小児科の富川盛光助手は「一戸建てよりマンシ ョンなどの方が症状を起こしやすい傾向がある。アレルギー症状の ある子は注意が必要だ」と話している。
都会の子、疑いが農村の2倍
厚労相 (2003.4.26 読売)
>>ヘッドライン
都会に住む小中学生の1・7%
都会に住む小中学生の1・7%が、自宅の新築や改築などに伴う「シックハウス症 候群」の疑いがあることが、厚生労働省研究班の調査で分かった。症状の割合は農村 部の約2倍。子供を対象にした同症候群の実態調査は初めてで、結果は日本小児科学 会で、27日発表される。
調査したのは、東京慈恵会医科大付属柏病院の富川盛光医師ら。東京・港区内の2 9小中学校と、新潟県津南町の10校の子供たちを対象に、目や鼻のかゆみ、頭痛な ど体調の変化の有無を調査。
〈1〉何らかのにおいを感じている
〈2〉場所が原因で症状が出ている
〈3〉自宅の新築や改築後に発症したり悪化した
――などに該当するケースを「シックハウス症候群の疑い」があるとした。
ミネラル水19品からアルデヒド類
横浜市衛生研究所 (2003.4.20 毎日)
>>ヘッドライン
アルデヒド類の基準はない
横浜市衛生研究所が、国内で販売されているミネラルウオーターの一部から、化学物 質のホルムアルデヒドやアセトアルデヒドを検出していたことが分かった。同市の水道 水の実測値と比べ、80倍以上の製品もあったが、飲み続けても人体に影響が出る量で はないという。ミネラルウオーターの水質は食品衛生法に基づく基準があるが、水道水 に比べ基準項目が少ない。厚生労働省は、昨秋から、ミネラルウオーターの新水質基準 の策定を始めている。しかし、アルデヒド類の扱いは未定としている。
調査したのは、横浜市内で販売されているボトル入りのミネラルウオーター30品。 うち14品が米、仏、カナダなどからの輸入品、16品が10道県で採水された国産品 。同研究所が開発した分析法でホルムアルデヒド、アセトアルデヒドを調べた。
その結果、輸入品5品、国産品14品の計19品からアルデヒド類が検出され、うち 17品にはホルムアルデヒド、アセトアルデヒドの両方が含まれていた。
ホルムアルデヒドの最高濃度は国産の1品の1リットル当たり59マイクログラム。 アセトアルデヒドは米国産の同260マイクログラム。いずれも同市の水道水の実測値 (ホルムアルデヒド13マイクログラム、アセトアルデヒド3.1マイクログラム)を 上回った。
日本ではミネラルウオーターは清涼飲料水に分類され、食品衛生法で規格基準が定め られているが、アルデヒド類の基準はない。一方、水道水には水質基準を補う監視項目 としてホルムアルデヒド(ホルマリン)があり、指針値(これを超えないように監視す る)は1リットル当たり80マイクログラムとなっている。
混入の原因は、水源か製造の過程が考えられるが、同研究所は「はっきりしない」と している。容器の材質との関連性は認められなかった。
ホルムアルデヒドは疫学調査で発がん性が確認されており、シックハウス症候群や化 学物質過敏症の原因物質とされる。アセトアルデヒドは動物実験で発がん性が確認され ている。
厚労省食品保健部基準課では「初めて聞いた話なので、詳しいコメントはできない 。ただ、ミネラルウオーターは、元々きれいな水源の水という前提の商品で、国際的な 基準に合わせて水道水よりは水質項目が少なく設定されていた。現在、改定中で、今夏 以降、新基準が作られる。アルデヒド類の扱いは、未定だ。」と言う。
パソコン各社シックハウス対策着手
パソコンメーカー (2003.4.15 日経)
>>ヘッドライン
学校やオフィス向けに「安全」をアピール
パソコンメーカーが化学物質により目の刺激や頭痛などが生じるシックハウス症候群の対策に動き始めた。 同症候群は主原因である住宅分野で規制や対策が進んでおり、 もともと使用量が少ないパソコンが問題視されているわけではない。 ただ、今後、学校やオフィスなど大量に使う顧客で、より体に優しい商品を選ぶ傾向が強まるとみて先手を打つ。
パソコンを長時間使用すると熱により接着剤などに含まれるホルムアルデヒドなどの化学物質が 空気中に放出される可能性がある。教室など一つの部屋で大量のパソコンを同時に動かした場合は その影響が増えるケースもあるとみられる。
NECは密閉した中で化学物質の放出状況を調べる設備を導入した。 専門の検査機関に委託すると1台あたり約100万円の費用が必要で時間もかかるため、 自前ですぐに分析できるようにした。
まず現在販売している製品について、長時間使っても6種類の化学物質がそれぞれ厚生労働省が 定めた指針値のさらに10分の1以下に収まることを確認した。
シックハウス症で労災認定
堺市 (2003.4.9 共同)
>>ヘッドライン
市職員の保育士
大阪府堺市立保育所の仮設園舎で、シックハウス症候群やその重 症例の化学物質過敏症(CS)にかかった市職員の保育士ら3人が 9日までに、公務災害の認定を受けた。地方公務員災害補償基金( 東京)によると、シックハウス症候群の公務災害認定は異例。
堺市保育課などによると、認定を受けた3人は同保育所に勤務し ていた女性で、微量の化学物質で体調を崩すCSはうち一人。3人 には治療費が支払われる。
2001年5月、3人は保育所の民営化に伴う建て替え工事で仮 設園舎に移ったところ、頭痛やけん怠感などの症状を訴えた。仮設 園舎には、シックハウスの原因物質であるホルムアルデヒドが放出 されやすい建材が使われていたという。
同保育所では、昨年3月にアルバイトの保育士が初の労災認定を 受けたほか、園児15人も頭痛などを訴えた。
ホルムアルデヒド性能評価機関
国交省 (2003.3.18)
>>ヘッドライン
改正建築基準法に基づくホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に係る指定性能評価機関が 国交省により下記のとおり指定された。また、これらの指定性能評価機関において実施される 性能評価の業務方法書モデル も併せて公表された。 ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価に係る指定性能評価機関の一覧
●(財)建材試験センター 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 03-3664-9216
●(財)日本建築センター 〒105-8438 東京都港区虎ノ門3-2-2 第30 森ビル 03-3434-7169
●(財)日本合板検査会 〒105-0003 東京都港区西新橋1-18-17 明産ビル 03-3591-7438
●(財)日本住宅・木材技術センター 〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル4F 03-3589-1796
●(財)日本塗料検査協会 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿3-12-8 東京塗料会館205 03-3443-3011
●(財)ベターリビング 〒102-0084 東京都千代田区二番町4-5 相互二番町ビル6階 03-5211-0599
●(財)日本建築総合試験所建築評定センター 〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10 TSビル4F 06-6966-7600
「健康回復住宅」が続々
NPO (2003.4.3 共同)
>>ヘッドライン
シックハウス患者の助けに
シックハウス症候群など化学物質過敏症の患者のため、療養用の 住宅をつくる動きが各地で進んでいる。空気のきれいな土地で体調 を回復させるのが目的で、自宅での生活が困難になった人の大きな 助けになりそうだ。
民間非営利団体(NPO)の「化学物質過敏症支援センター」( 横浜市)は、静岡県中伊豆町に約3900平方メートルの土地を取 得し、「脱化学物質コミュニティー」計画を進めている。
賃貸用住宅2棟と定住用五棟分の敷地を用意。定住の場合はセン ターから土地を借り、建物は自分で建てる。過敏症に理解のある建 築業者の協力を得て、ホルムアルデヒドなどを使わないつくりにす るという。
北海道旭川市で一時避難用の施設を運営しており、二カ所目。網 代太郎事務局長は「完全に治すのは難しいが、環境の良い所で暮ら し症状が軽くなれば、元の生活に戻ることもできる」と話す。
山口県阿武町で「健康村」を計画しているのは、NPO「PFI 推進事業体」(福岡市)の山中修代表理事らのグループ。住宅10棟 をつくり、うち2棟程度を過敏症患者向けにする。
また空気清浄機などのメーカー、新菱エコビジネス(東京)は、 福島県猪苗代町に木造住宅14棟を建設する予定。
化学物質過敏症の症状は、全身のけん怠感やどうき、息切れなど さまざま。住宅建材や食品添加物、農薬など原因物質は数万種類も あるとされるが、専門に治療できる医療機関は国内で数カ所しかな く、患者数など実態は分かっていない。
|