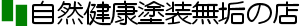サンウッド旧ニュース10
● 症状と汚染物質の関連調査分析
厚労省 (2004.2.36 共同)
ヘッドライン
シックハウス症候群の実態把握を目指す
新築やリフォームした家で目やのどが痛くなる「シックハウス症 候群」の原因を探るため、厚生労働省は26日までに、症状を訴 える人たちの自宅に出向いて実際に室内汚染状況を測定する大規模 な調査に乗り出した。
住宅内の化学物質濃度を調べる全国調査はあるが、症状との関連 を調べる大規模調査は初めて。化学物質だけでなくダニやカビなど の原因物質を総合的に分析するほか、温度、湿度の違いによる地域 差も検討、謎に包まれたシックハウス症候群の実態把握を目指す。
調査は岸玲子・北海道大大学院教授を主任とする研究班が実施。 北海道、福島県、愛知県、大阪府、岡山県、福岡県の六地区で調査 を始めている。
自治体に提出された建築確認申請書類を閲覧して計4千軒程度の 新築・リフォーム住宅を無作為に選び、住民に自覚症状の有無や換 気方法などをアンケートする。
実際の測定調査は、回答者のうち同意を得られた家庭が対象。症 状のある人、ない人の双方の家を選んで測定し、ホルムアルデヒド やトルエンなどの化学物質、ダニ、カビなどの汚染濃度、温度、湿 度などとの関連を分析する。
調査は2003年度から3年がかりで、厚労省は各年4千万円前 後の研究費を助成する。
岸教授は「雪国と暖かい南国ではシックハウス症候群の傾向が違 うのか、どの程度の濃度から症状が出始めるのかなどを明らかにで きれば」と話している。
● 大気汚染防止法改正案
環境省 (2004.2.18 共同)
ヘッドライン
トルエンなどの排出抑制
浮遊粒子状物質(SPM)や光化学スモッグの原因となるトルエ ンなど揮発性有機化合物(VOC)の排出を減らすため、環境省が 今国会に提出する大気汚染防止法改正案が18日、判明した。
事業者の設備投資負担などに配慮し自主的取り組みを尊重、大規 模施設を対象とする最低限の法規制と自主規制を組み合わせたのが 特徴だ。今月下旬にも、閣議決定し国会に提出する予定。同省は、 VOC排出量を2010年度までに2000年度より3割程度削減 することを目指す。
欧米などで進んでいるVOCの排出抑制が国内でも急務となる中、 一律の法規制に対する産業界の反発が強いことを踏まえ、事業者の 自主的な取り組みを基本に、法規制を限定する異例の手法を採用す ることで対策導入を優先した。
改正案は「一律規制は必要以上の設備投資を中小企業にも求める ことになり非効率」(同省)として、規制対象は自動車などの塗装 施設や印刷工場、燃料タンクなどのうちVOC排出量が特に多い大 規模な施設に限定し、政令で定める。
対象事業者にはVOCの排出濃度の測定を義務付け、省令で定め る濃度基準に適合しない場合、都道府県が施設の構造改善や使用停 止などを命じることができるとした。
一方、中小企業など規制対象外の事業者も含めた対策の効果を上 げるため、事業所や企業、業界団体ごとに創意工夫に基づく自主的 取り組みが促進されるよう国は十分配慮すると規定。実効性を確保 するため、取り組みの効果を検証し情報公開する仕組みをつくる。
● 50校調査では異常なし
文科省 (2004.2.10 共同)
ヘッドライン
基準を超えた学校はなかった
文部科学省は10日、頭痛やのどの痛みなどが起こるシックハウス 症候群の原因となる化学物質の空気中濃度を全国50の小中学校で 測定した結果、厚生労働省が定めている基準を超えた学校はなかっ たと発表した。
調査は新築・改築、全面改修、築5年、10年、20年の小中学校 を10校ずつ計50校選び、2000年12月から01年2月まで実 施。エチルベンゼン、スチレン、テトラデカン、クロルピリホス、 ダイアジノン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチル ヘキシルの7つの化学物質について教室や保健室、体育館などでそ れぞれ測定した。
● 個人情報開示請求手続き不要に
調布市 (2004.2.7 読売)
ヘッドライン
口頭の申し出だけで、開示する
東京都調布市立調和小学校でシックハウス症候群と見られる症状が児童に出た問題 で、同市教委は6日、今後は親が個人情報の開示請求をしなくても、口頭の申し出だ けで、その場で児童の健康診断結果を開示することを決めた。
市教委は、同小児童への有害物質の影響を調べるため、一昨年から昨年にかけて健 診を行ったが、我が子の診断結果を希望する親には、個人情報の開示請求を求めてき た。「医師に委託してまとめたこともあり、厳格に扱ってきたが、保護者の知る権利 を尊重するため、弾力的な対応に転換した」としている。
市教委は来週にも、同小の全保護者に対応の変更を伝える通知を出す。
● 健診結果、保護者に開示請求要求
調布市 (2004.2.6 読売)
ヘッドライン
個別の健診結果を保護者に通知しなかった
東京都調布市の小学校でシックハウス症候群と見られる症状が児童に出た問題で、 健康診断結果の通知を希望する保護者に対し、同市教委が個人情報の開示請求をする よう求めていたことが5日、分かった。保護者からは「我が子の健康診断の結果を知 るのに、こんな手続きが必要とは」と疑問の声が上がっている。
シックハウス症候群は、住宅建材などから放散される化学物質を吸い込むことで頭 痛や吐き気などが起きる症状。調布市立調和小学校では、一昨年夏に完成した新校舎 から、国の指針値を大幅に超える有害物質のトルエンなどが検出され、多数の児童が 体調不良を訴えた。
これを受け同市教委は、大阪のNPO「シックハウスを考える会」の医師と学校医 に委託し、同年10月と昨年3月、同10月の3回にわたり、同校の全児童に問診な どの健康診断を行った。
1回目の健診後、市教委は「全校児童の約2割が、シックハウス環境の影響を強く 受けたと見られる」との結果を公表。その一方、「親に通知が必要という医師の指示 がなかった」として、1、2回目の健診については、個別の健診結果を保護者に通知 しなかった。
これに対し、体調不良を訴えた計9人の児童の保護者が「病院受診のため、健診の 結果を知りたい」と要望。しかし、市教委では「健康診断の結果は個人情報にあたる」 として、開示請求の手続きを要求した。
このため、保護者らは昨年8月から9月にかけ、市の個人情報保護条例にもとづき 「自己情報」の開示請求を行い、2週間後、医師が記入した我が子の「個別検診表」 と「所見」のコピーを交付された。請求の際、親子関係を証明するために住民票の提 出も求められたという。
保護者の不満を受け、市教委は昨年10月の健診後、一部児童の親に「シックハウ ス症候群との関連はないと思われるが、(医療機関での)早めの受診を勧める」との 文書を出した。だが、健診結果そのものについては、「開示請求が必要」との立場を 崩していない。
開示請求した保護者(43)は、「子どもの健康を心配するのは親として当たり前 なのに、こんな手続きが必要とはおかしい」と話す。
一昨年にシックハウス症候群と見られる症状が児童に出た長野県塩尻市の市立塩尻 西小の場合、全員の保護者に健診結果を文書で通知したという。昨春、校舎から高濃 度のトルエンが検出された東京都立世田谷泉高校でも、健診結果を生徒本人に詳しく 説明したといい、都教委では「一般的に、健康診断の結果は本人に情報を示すことで、 健康への意識を改善する意味があるのでは」と話していた。
● VOC排出量3割削減へ
環境省 (2004.2.3 毎日)
ヘッドライン
一定規模以上の事業者に排出削減を義務付け
塗料や溶剤などに含まれるトルエンなど揮発性有機化合物(VOC)について、中央 環境審議会は3日、施設からの排出量を10年度までに3割削減する目標を決めた。目 標達成のため、一定規模以上の事業者に排出削減を義務付け、中小事業者には自主的な 削減を促すことを環境省に求めた。環境省はこれを受け、自動車メーカーの塗装工場な ど大規模施設を規制対象とする大気汚染防止法の改正案を今国会に提出する。中小事業 者には、削減実績の公表を求めることを決めた。
大気中に放出されたVOCは、発がん性が指摘される浮遊粒子状物質(SPM)や光 化学スモッグの原因物質となる。同省によると、00年度に国内の施設から150万ト ンが排出された。工場や屋外作業場からの排出が大部分を占める。
審議会の検討会は昨年12月、法規制を中心とした排出削減策をまとめた。しかし、 その後の審議会の議論の過程で、一律の規制は必要以上の削減を強いることになるなど の意見が出された。このため審議会は、法規制の対象は大規模施設に限り、中小施設は 自主規制にとどめることを提言した。ただし、削減が進まない場合は、規制対象の拡大 も可能としている。
規制の対象施設や基準は、大気汚染防止法の改正後に政省令で定める。同省によると 、VOCの排出施設は国内に数十万あるとされるが、規制対象は数千施設になる見通し だ。
政府は、自動車NOx(窒素酸化物)・PM(粒子状物質)法で、10年度までにS PMの環境基準をおおむね達成するとしている。現在の自動車排ガス規制だけだと達成 率は88%にとどまるが、今回の目標が実行されれば、達成率は90%を超えるという。
● マンションでシックハウス集団提訴
大阪 (2004.1.29 朝日)
ヘッドライン
総額約3億600万円の損害賠償
新築の分譲マンションに入居したのに、床下の建材に含まれる化学物質で「シックハ ウス症候群」になったとして、大阪市北区の「ライオンズマンション」(95戸)に住 む20世帯46人が29日、販売元でマンション分譲大手の大京(東京)と施工業者 「大末建設」(大阪)、建材メーカー「ブリヂストン」(東京)の3社を相手に、 リフォーム費用や慰謝料など総額約3億600万円の損害賠償を求める訴えを 大阪地裁に起こした。
訴えによると、原告らは00年11月~02年1月に入居したが、間もなく頭痛やめ まい、目の痛みなどに悩まされ、多くの人が専門医のいる北里研究所病院(東京)で「 シックハウス症候群」の症状と診断された。空気測定で、原因物質となるホルムアルデ ヒドが平均で国の指針値(1立方メートルあたり0.1ミリグラム)の約2倍の高濃度 で検出され、床下の建材から放出されていることがわかったという。
マンションは99年夏に着工されたが、国の指針はその約2年前に示されていて、原 告らは「化学物質の少ない建材を選ぶことができたのに、欠陥住宅を引き渡した過失が ある」と主張。症状の改善には床の張り替えなどが必要だとして補修費用や健康被害に 対する慰謝料などを求めている。
原告らは話し合いによる解決を求めて調停を申し立てていたが、今月、不成立に終わ った。
<大京広報部の話> 訴状が届いておらず、コメントは差し控えたい。原因も特定で きておらず、当社に法的責任はないと考えており、今後も引き続き、主張の正当性を訴 えていきたい。
● シックハウス「けやき小学校」安全確認
西東京市 (2003.12.25 NHK)
ヘッドライン
トルエンの濃度が基準を下回った
国の基準を超えるトルエンが検出されたため新築されたばかりの校舎の使用を見合わせて いた東京・西東京市の小学校について、市の教育委員会は、トルエンの濃度が基準を下回 り、安全が確認されたとして来月から新しい校舎での授業を始めることを決めた。
こ の問題は、西東京市芝久保町に建てられた市立「けやき小学校」の新しい校舎で、ことし 7月に行われた検査の結果、国の基準を上回る高い濃度のトルエンが検出されたもの。
けやき小学校では2学期から使用する予定だったこの校舎の使用を見合わせ、古い校舎で 授業を続ける一方、教室の換気などの対策を進めてきた。
その結果、新しい校舎のすべての教室でトルエンなどの化学物質の濃度が国の基準を下回 っていることがわかった。
このため西東京市教育委員会では、安全が確認されたとして、3学期の始まる来月8日か ら、けやき小学校の全校児童が新しい校舎に移動して授業を始める方針を決め、保護者に 説明した。
市教育委員会では児童への影響が出ないよう、今後も教室の換気は続けることにしている。
● 特別教室はホルムアルデヒドの濃度高
東京23区小中校 (2003.12.24 NHK)
ヘッドライン
440か所で基準値を上回った
東京23区内の小・中学校でシックハウスの原因となる化学物質の濃度を測定した結果、 音楽室やパソコン教室といった特別教室で、ホルムアルデヒドの濃度が高い傾向にあるこ とがわかった。
文部科学省は、校舎を新築したり改築したりした時だけでなく、現在使われている校舎に ついても今年度からシックハウスの原因物質を測定するよう指導している。
NHKが 東京23区の測定結果をまとめたところ、教室や体育館など測定した3200か所のうち 13%にあたる440か所でホルムアルデヒドの濃度が国の基準値を上回った。
このうち、▽普通教室でホルムアルデヒドの濃度が基準値を上回ったのは調査した教室の うち9%だったの対し▽音楽室は30%▽パソコン教室は23%で、特別教室でホルムア ルデヒドの濃度が高い傾向にあることがわかった。
ホルムアルデヒドは大量に吸い込むと発ガン性の恐れがあるが、今年7月に使用を制限さ れるまで接着剤の原料として建築に広く使われてきた。
これまでのところホルムアルデヒドによる健康被害は出ていないが、シックハウスに詳し い千葉工業大学の小峯裕己教授は、「特別教室は利用しない時間が多いうえ、騒音対策な どで原則、窓を閉めて使うことになっているため普通教室よりもホルムアルデヒドの濃度 が高くなったと見られる。換気を徹底して濃度を下げることが重要だ」と話してる。
● 住宅7.1%でホルムアルデヒド検出
国交省 (2003.12.19 朝日)
ヘッドライン
指針値を超える住宅は大幅に減る
国土交通省は19日、シックハウス症候群の原因と見られる住宅内の化学物質濃度の 実態調査を発表した。
接着剤や合板から出るホルムアルデヒドは7.1%の住宅で厚生労働省が定める指針 値(0.08ppm)を超える濃度を検出。アセトアルデヒドは9.2%から指針値( 0.03ppm)を超える濃度が検出された。油性ペンキなどから出るトルエンが4. 8%の住宅で指針値(0.07ppm)を超えた。
昨年夏、調査に協力した築1年以内の住宅1390戸で調べた。
改正建築基準法により、今年7月からホルムアルデヒドを使った建材は規制されてい る。調査は規制前のため、国交省は今後、指針値を超える住宅は大幅に減ると見ている
● 冬のシックハウスにご用心
大阪府堺 (2003.12.16 共同)
ヘッドライン
暖房・密閉に専門家が警鐘
寒いこれからが危険な季節―。シックハウス問題に取り組む医師 が、本格的な冬の到来に「閉めきった室内で暖房を使うと、ホルム アルデヒドやトルエンなど有害物質が揮発してこもりやすくなる」 と家庭や学校に注意を促している。
大阪府堺市の今年8月の調査では、約6割の学校・幼稚園でシッ クハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドが国の基準値を上 回った。最高値だった教室は、窓を開けた検査では基準の半分以下 だったが、閉め切ると基準の5・8倍に。
「閉め切った部屋がいかに危険かを示している。冬の暖房は同じ ように室内の濃度を高める危険がある」と、大阪府保険医協会の笹 川征雄医師は指摘する。
新築やリフォームから10年以内の建物は特に要注意。敏感な子供 やお年寄りだけでなく、家にいる時間が長い主婦の発症も多い。目 がしみたり充血したらシックハウスを疑ったほうがいいという。発 症すると頭痛やめまい、体調不良などに陥る。
特定非営利活動法人(NPO法人)「シックハウスを考える会」 の上原裕之理事長も「風を入れたり換気扇を回したり、閉め切らな いことが大事。2時間に1回、5分程度は空気を入れ替えて」と呼 び掛けている。
● シックハウス症候群軽減するオフィス家具
プラス (2003.12.15 朝日)
ヘッドライン
ホルムアルデヒドを吸着したり、光反応で分解したりする素材
オフィス用品大手のプラスは22日から、「シックハウス症候群」を軽減するパーテ ィション(間仕切り)や机の上に置くパネルを発売する。シックハウス症候群は建材や 接着剤などに含まれる化学物質が原因で、頭痛や吐き気などをきたす症状。プラスは主 原因のホルムアルデヒドを吸着したり、光反応で分解したりする素材を練り込んだ外張 りを開発し、業界で初めて商品化したという。
● 揮発性化合物の排出を規制
環境省 (2003.12.1 共同)
ヘッドライン
大気汚染防止法改正
環境省は一日、大気汚染物質である揮発性有機化合物(VOC) の排出を減らすため、一定規模以上の工場を対象にVOCの排出濃 度を規制することを盛り込んだ大気汚染防止法改正案を、来年の通 常国会に提出する方針を決めた。
VOCは塗料の溶剤や接着剤に使われ、トルエン、キシレンなど 主要な物質だけでも100種類以上ある。年間で約185万トン(2000年度) 排出されており、呼吸器に悪影響を与える浮遊粒子状 物質(SPM)や光化学オキシダントの原因となる。
環境省はこれまで、SPM削減のため自動車の排ガス規制を強化 してきたが、VOCが光化学反応で粒子になる二次粒子もSPMの 多くを占めることが分かってきた。このため大気環境基準達成に向 け、VOCの法規制に乗り出すことにした。
同法改正案では、自動車工場など各種塗装工程をもつ工場や印刷 工場にVOC排出濃度の測定を義務付け、業種ごとに定める基準を 超えた場合には改善命令を出すほか、罰則も設ける。
ガソリンスタンドで給油時に揮発するガソリンもVOCの一種で 、野外の塗装作業などでもVOCが飛散するが、こうした排出や小 規模工場は規制対象外となる。環境省は法改正で規制できるVOC 排出量は全体の約7割とみている。
同省の2002年度の調査では、SPMの環境基準達成率は3年連続 で悪化。光化学オキシダントの基準達成率も0・5%と極めて低い 状況が続いている。
● 大気汚染防止法でVOC規制
環境省 (2003.11.19 朝日)
ヘッドライン
改正案を来年の通常国会に提出する
大気中で発がん性物質を発生させるトルエンなど揮発性有機化合物(VOC)の規制 を検討していた環境省は18日、排出基準を設けることを盛り込んだ大気汚染防止法の 改正案を来年の通常国会に提出することを決めた。零細業者や屋外での作業は対象外だ が、化学工業、塗装、印刷など数万カ所の事業所が削減義務を負い、VOCの吸着装置 などの設備を設けなければならなくなる。
VOCは大気に排出されると光化学反応を起こしてオゾンを発生させ、それが窒素酸 化物などと結びついて発がん性のある浮遊粒子状物質(SPM)が発生する。国はSP Mを減らすために自動車の排ガス規制をしているが、それだけでは2010年までに達 成するとした環境基準に届かないため、新たな規制に乗り出すことにした。
改正案成立後に、VOCが含む炭素濃度をもとに基準を作る。規制までに3、4年の 準備期間を置く。VOCの種類が数百に上ることなどから、基準値は業種ごとに細かく 設定する。
事業者の負担に配慮して、小規模のクリーニング店など零細な業者は規制の対象外に する。環境省は、従業員20人以上の事業所からの排出量が全体の3分の2を占めてい るため大きな影響はないとしている。
米国は90年からVOCの規制を始め、欧州連合(EU)でも排出基準が決まってい る。1平方キロあたりのVOC排出量は米国が1.9トン、EUが3.6トンで、日本 は4.9トンに上る。
● 全都立高校に簡易測定器配備
東京 (2003.11.14 NHK)
ヘッドライン
都立高校校舎からトルエン
東京・世田谷区にある都立高校の校舎からシックハウスの原因とされる化学物質のトルエ ンが検出された問題を受けて、東京都教育委員会は、都立のすべての学校を対象に化学物 質の簡易測定器を配備するなど、生徒の健康被害を防ぐための対策をまとめた。
東京・世田谷区にある「都立世田谷泉高校」では、ことし5月、改修工事が行われたばかり の校舎の一部から、国の基準を最高で5倍も上回る濃度のトルエンが検出された。
トルエンは、目やノドの痛みなどを起こすシックハウスの原因物質とされ、東京都教育委 員会は、校舎の使用をやめてトルエンを除去する作業を進めるとともに、都立の学校での シックハウス対策について検討していた。
東京都教育委員会がまとめた対策によると、校舎の新築や改修の際には、化学物質の発生 が少ない建材や塗料を使い、工事が終わった段階でホルムアルデヒドやトルエンなどの濃 度が基準を下回るよう工事の業者に求めていくとしている。
また、各学校には、来月、簡易測定器を配備して、校舎内の化学物質の濃度を定期的に測 定することや換気を適切に行うことなどを指導していくことにしている。
● 2割がシックハウス症候群
昭和大医 (2003.11.8 毎日)
ヘッドライン
建物滞在が原因の健康障害が、広範に存在する
特定の建物の室内環境が原因で何らかの健康障害が出る、最も広い意味での「シック ハウス症候群」について昭和大医学部が大規模な意識調査をしたところ、大人・子供と も調査対象の約2割が同症候群を訴えていることが分かった。このうち、ハウスダスト などによるアレルギー症状などを除くと訴えの率は大幅に低下した。専門家は「まずは 室内環境を適切にすることが、対策として重要だ」と指摘している。
昭和大学医学部の小田島安平助教授(小児科学)らの研究チームが調査した。00~ 02年度に東京都内、岐阜県、山口県、北海道の医院や小児科外来に来た親子や公立小 学校の児童、保護者ら2万229人に調査用紙を配布し、1万8124人(小児938 7人、成人8737人)から回答を得た。
同症候群は、ホルムアルデヒドなどの化学物質によるものを指す場合が多いが、医学 的な概念は世界的に確立しておらず、研究者や国によって定義が異なる。研究チームは 「室内の化学物質やアレルゲン、微生物などの影響で、体調不良や目・鼻、皮膚、消化 器などの症状が起こる健康障害」とシックハウス症候群を広く定義し、質問したところ 、成人22.1%、小児19.8%が「ある」と答えた。
一方、回答に基づき、ハウスダストや微生物によるアレルギー症状や防虫剤などによ る一時的な中毒症状などを除外し、「原因不明だが、明らかに特定の建物への滞在で引 き起こされた健康障害」を訴える人の割合を算出すると、成人8.5%、小児4.6% となった。いずれも建築年数では大きな差はなかった。
今回は特定の対象群を調査しており、国民全体の数字とはいえないが、研究グループは、 建物滞在が原因の健康障害が、広範に存在することが分かったと指摘する。小田島助教授 は「健康被害を訴える人の中には、ホコリなどのアレルゲンや化学物質を掃除で取り除き、 適切な室内環境を保つことで改善する症例も多い」と話している。
● 児童の治療費支払拒否
調布市教 (2003.11.1 毎日)
ヘッドライン
「裁判を起こしてもらうしかない」と
東京都調布市の小学校で、校舎が原因とみられるシックハウス症候群と診断された児 童の治療費について、同市教委が保護者に「裁判を起こしてもらうしかない」として支 払いを拒否していることが分かった。診断法が確立されていないことなどが理由だが、 全国的には全額負担している市町村もあり、保護者側は「無責任な対応のうえ、裁判を 起こせとは」と反発している。
この小学校は同市西つつじケ丘の市立調和小学校(児童数396人)。昨年9月に新 校舎を使用し始めてから、複数の児童が有害化学物質の放散が原因とみられる頭やのど の痛みなどを訴えた。
市教委は校舎の換気を強化するとともに、児童らの臨時健康診断を実施。保護者が独 自に行った医療機関での検査費も負担した。しかし今年9月、児童6人が病院で同症候 群と診断された後、市教委は1人約2万3000円の検査費は負担したものの、治療費 については「(支払いを求めるなら)裁判を起こしてもらう必要がある」などと保護者 に説明した。10月の全校の保護者への配布文書でも「治療費等の補償については、法 的な判断に基づき対応させていただきます」などと通知した。
市教委は毎日新聞の取材に「新校舎の有害化学物質が児童に健康被害を与えたのは事 実だが、程度が不明なうえ治療法も未確立で治療費を出す根拠がない。司法の判断をい ただきたいという意味だ」と説明している。
これに対し、6年生の長女が同症候群と診断された母親は「原因は明らかなのに無責 任。裁判は費用も時間もかかり容易ではない」。同市教委の委託で新校舎を調査したN PO(非営利組織)法人「シックハウスを考える会」の上原裕之理事長も「きっかけを 作ったのは学校。教育者なら当然負担すべきだ」と話している。
同様のケースでは、児童5人が校舎が原因とみられるシックハウス症候群などと診断 された長野県塩尻市教委が、治療費と東京の病院までの交通費を全額負担。大阪府堺市 の湊保育園でも、治療費を全額負担している。
一方、文部科学省学校健康教育課は「(シックハウス症候群は)診断基準が不明確なため、 専門家による調査研究会議を設けて実態把握に努めている段階。治療費の負担はケース・ バイ・ケースで市町村の判断」としている。
● トルエンで千代田区長ら減給
東京千代田区 (2003.10.20 共同)
ヘッドライン
福祉施設で指針値を超えるトルエン
東京都千代田区のショートステイなどの福祉施設で、シックハウ ス症候群の原因物質とされるトルエンが厚生労働省の指針値を超え て検出された問題で、千代田区は石川雅己区長を減給100分の20、 1カ月とするなどの処分を決めた。
また10月1日の開業予定を1カ月延期した施設の業務開始を年明 けに再延期すると発表した。
施設は「岩本町ほほえみプラザ」。ショートステイのほかグルー プホームや、ケアハウスとして利用する。開業直前にショートステ イ用の居室2カ所から指針値を超えるトルエンを検出した。床材の 接着剤にトルエンが含まれていたのが原因と判明し、換気などの対 策を取って現在は指針値を下回っている。
しかし抵抗力が弱い高齢者向け施設であり、区はさらに万全を期 すことにした。建物を建設した都住宅供給公社と今後、補償問題な どを協議するという。
● まぶたのけいれん、化学物質も要因か
東京眼科医 (2003.10.19 朝日)
ヘッドライン
建材から発生する化学物質に長い間接触した
重症になるとまぶたの筋肉が震え、目を開けられなくなってしまう「眼瞼(がんけん )けいれん」が、室内や職場などで化学物質に長い間接触すると起きる可能性が高いこ とを、井上眼科病院(東京都)のグループが突き止めた。眼瞼けいれんによって歩行や 車の運転にも大きな支障が出ていることも判明。グループは31日から名古屋市で開か れる日本臨床眼科学会で発表する。
眼瞼けいれんは、脳など中枢神経系の異常で起こり、加齢やストレス、抗不安薬など の副作用なども引き金になると考えられている。
同病院の若倉雅登(わかくら・まさと)院長らのチームはほかの要因を探るため、薬 剤の影響以外の患者167人を対象に、発症前5年間の化学物質の接触状況を調べた。 患者の4割強が新築・改築した家に住んだり、新装・改装した職場に勤務したりしてい た。建材から発生する化学物質に長い間接触した疑いが濃い。この中には、職業上、塗 料、シンナー、防虫剤、農薬などを扱う人もいた。
さらに、患者54人への別の調査では、半数が歩行中に電柱や停車中の車などにぶつ かった経験があった。また、6割ほどが車の運転中に危険を感じ、その半数がずっと運 転をやめている。
若倉院長は「生活への支障はとても大きく、室内の化学物質で体の不調を訴えるシッ クハウス症候群と関連している疑いもある。眼瞼けいれんへの世間の理解は浅い。予防 や診断などに注意を促したい」と話す。
● 日弁連の人権擁護大会始まる
日弁連 (2003.10.17 NHK)
ヘッドライン
化学物質の問題は今回初めて
「シックハウス症候群」といった化学物質による健康被害など現代社会が抱える人権 に関わる問題を話し合う日弁連=日本弁護士連合会の「人権擁護大会」が、16日から 松山市で始まった。
この大会には、弁護士や市民団体の関係者など全国から3千人が出席し、化 学物質の汚染による被害や犯罪被害者の権利の確立など3つのテーマについて、シンポ ジウムが行われた。
このうち化学物質の問題は今回初めて取り上げられたもので、環境化学が専門の愛媛 大学の田辺信介教授が、ダイオキシンなど有害な化学物質による汚 染が地球全体に広がっている現状について報告した。
また、昭和40年代に、PCB=ポリ塩化ビフェニールなどが原因で起きた「カネミ 油症」の被害者や、家を建築する際に使われた化学物質で目の痛みや頭痛などの症状が 出る、いわゆる「シックハウス症候群」になった女性も参加して、子どもたちが安全に 暮らせる環境を守るため身の回りに汚染が広がる化学物質を減らしていくことを訴えた。
大会では17日、犯罪被害者の権利の確立と支援に関する決議を行う。