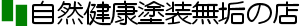サンウッド旧ニュース5
● シックスクールで兄弟が訴え
大阪 (2003.3.29 毎日)
ヘッドライン
「安全義務怠った」
シックハウス症候群で化学物質に過敏になっていた大阪市東淀川区の兄弟が、通って いた市立小学校と私立学校に病状を説明したのに配慮されず、症状の悪化で通学できな くなったとして、大阪市と啓光学園を相手に各1000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に 提訴する。支援団体によると、学校の化学物質で体調が悪化する「シックスクール」を めぐる初の訴訟になる。
訴えによると、兄弟は94年に新築した自宅で、両親らとともにシックハウス症候群 になった。軽症だった弟(15)は大阪市立小4年だった97年、校内エレベーター設 置工事で化学物質を吸ったのをきっかけに症状が悪化して化学物質過敏症になった。学 校に配慮を要望したが、授業での油性ペン使用や校庭での農薬使用などで症状が悪化し 、通学できなくなった。 兄(19)も化学物質過敏症で、中高一貫の私立学校に通っていたが、中学2年だっ た97年以降、教室の床へのワックスがけなどで頭痛や吐き気などがひどくなり、通学 できなくなった。学校側は昨年、「化学物質過敏症が治ったという診断書がないと、除 籍処分にする」と通知してきたという。
兄弟は、こうした学校側の姿勢は児童生徒の安全を確保する注意義務を怠っており、 文部科学省が各教委や学校法人に化学物質過敏症の児童生徒への配慮を求めた依頼文書 (01年1月)にも反していると訴えている。
大阪市教委は「訴状を見てないのでコメントできない」、学校法人側は「誠心誠意対 応してきたのが、理解されなかったのは残念。訴状を見て対応したい」と話している。
● ホタテ貝殻シックハウス対応建材に
稚内市 (2003.3.29 共同)
ヘッドライン
稚内市に新会社設立
北海道稚内市の近海で、年間約5万トン廃棄されているホタテの 貝殻を再利用し、住宅の内装用建材などに加工する新会社「JAY (ジェイ)・チャフローズ」が3月下旬、同市に設立された。 稚内市の住宅メーカー「郡組」や道内外の企業、ホタテ業者らが 参加、2005年からの操業を目指す。
ホタテの貝殻には、シックハウス症候群の原因とされるホルムア ルデヒドや、二酸化炭素の吸収効果があることが、八戸工業大学な どによる産学協同研究で確認されている。
計画では、粉砕した貝殻を1050度の高温で3時間焼いて粉末 にし、自然素材で作った接着剤と混ぜて住宅用塗料や壁材に加工す る。同社の工場では年間約1万5千トンの貝殻が再加工できるとい う。 貝殻は通常、産業廃棄物として処理されるが、実際は海中や海岸 のくぼみへの不法投棄が後を絶たず、有効な最終処分方法が模索さ れていた。 郡組の郡正昭社長は「地元で出た廃棄物は地元で処理するのが望 ましい。健康と環境の両分野で貢献できれば」と話している。
● 有害物質を除去する活性炭繊維シート
ユニチカ (2003.3.17 共同)
ヘッドライン
吸着力は備長炭の1万倍
ユニチカは17日、シックハウス症候群の原因とされるホルムア ルデヒドなどの有害物質を強力に除去する活性炭繊維シートを4月 から発売すると発表した。大手ゼネコンのフジタと共同開発し、 「吸着力は市販の備長炭シートの1万倍」としている。
新築のマンションや一戸建て住宅の床に敷くことで、数日で有害 物質を除去できるという。押し入れや家具で使用すれば消臭効果も ある。無害化する薬剤を活性炭に付着させて吸着力を高めた。使用 後は可燃物として捨てられる。
昨春から「備長炭の3000倍の強さ」タイプを既に販売してお り、インターネットによる一般消費者への販売にも力を入れる。
● 大京マンションシックハウス問題続報
大京 (2003.3.5 朝日)
ヘッドライン
不自然な測定結果
マンション分譲最大手の「大京」(東京都渋谷区)が販売した大阪市内のマンション から国の指針値を超える有害化学物質が検出され、入居者が健康被害を受けた問題で、 完成時の施工業者による化学物質の測定結果が指針値を大幅に下回っていたことがわか った。健康被害を受けた入居者は「結果は信頼できない」と指摘するが、大京は「販売 に使ってはいない」としている。
大阪市北区の「ライオンズマンション」(95戸)では完成時の00年11月、施工 業者の中堅ゼネコンが大京の指示で、建材に使われる化学物質「ホルムアルデヒド」の 室内空気中の濃度測定を計10戸で行った。1戸につきリビングや台所など計5カ所で 、密閉状態と換気した後に行われた。
その結果、濃度は最高でも0.0275ppmと、指針値の0.08ppmよりかな り低かった。
また計100回の測定結果は「0」と「0.025」、「0.0275」の3種類の 数値しか記されていなかった。
入居者らによると、施工業者は健康被害を受けた入居者の苦情に対し、結果を示して 「完成時の測定ではこうだった」と説明していたという。
建材に詳しい早大理工学部の田辺新一教授によると建材のホルムアルデヒドは、新築 の建物などで空気にさらされてから、数週間で半分から3分の1の量になることが多い 。
だが、このマンションでは完成1年後からの保健所の測定で、計3回とも指針値を上 回り、1年8カ月後に大京が行った精密測定でも指針値を平均1.9倍上回った。完成 時に測定した10戸のうち8戸でも完成時の測定より高い数値で(2戸は測定せず)、 うち6戸で指針値を超えた。
完成時の測定結果についてホルムアルデヒドの測定に詳しい医師は「通常、多く出る 台所で低くなっているなど考えにくい結果だ」と指摘する。
これに対し、施工業者は「簡易測定法で実際に行った。細かい数値が読みとれない場 合に機器の説明書に従って算出した」。大京広報部は「参考として測定を依頼したが、 結果を使って販売はしていない」と説明する。
シックハウス症候群と診断された入居者、今井義治さん(36)は「測定結果の信頼 性は極めて怪しい。入居者から苦情が出た時の言い逃れのために使ったのも許せない」 と話している。
● 対策十分マンションでシックハウス
大京 (2003.3.4 朝日)
ヘッドライン
ホルムアルデヒドが指針値を超える
マンション分譲会社最大手の「大京」(東京都渋谷区)が00年11月に完成させた 大阪市内のマンションで、シックハウス症候群の原因物質「ホルムアルデヒド」が厚生 労働省の指針値の最高で4倍以上の濃度で検出され、一部の入居者が同症候群と診断さ れていることが、3日わかった。大京は「シックハウス対策は十分」と説明して販売。 健康被害を訴える入居者に一時、買い戻しを申し出ていたが、朝日新聞の取材には「因 果関係ははっきり分からない」としている。
問題のマンションは、大京が99年末から販売した大阪市北区の「ライオンズマンシ ョン」(95戸)。
入居者らによると、01年の入居直後から約半年の間に、少なくとも10世帯十数人 が発疹や頭痛、呼吸器の異常などを訴えた。重い症状が続いて会社を退職したうえ、マ ンションを所有したまま、医師の勧めで転居せざるをえなくなった男性もいる。
これまでに6人の入居者が、同症候群かどうかが厳密に判定できる北里研究所病院( 東京都港区)で診察を受けたところ、全員が同症候群と診断されている。
入居者の依頼を受けた保健所が01年11月からマンションの一室でホルムアルデヒ ドを計3回測定した結果、高い時には0.16ppmと、いずれの時も厚生労働省の安 全指針値(0.08ppm)を超える数値が出た。
また大京が昨年7月に研究機関に委託した調査でも、指針値を超える量が検出された 世帯が約7割に上り、最高で指針値の4倍以上、平均で約1.9倍の数値を示した。
このマンションを販売した大京の元社員や入居者らによると購入前、大京の営業マン は「建材はホルムアルデヒドの最も少ないものを使用」「(指針値の)0.08ppm をクリアすることはもちろん、限りなくゼロに近づける」とシックハウス対策を強調し たパンフレットを渡したり、「対策は十分」と説明したりして購入を勧めていたという 。
このマンションには実際には、ホルムアルデヒドが比較的多く放出される恐れがある 性能の低い建材が多用されていた。
この建材について大京は「01年以降は使用していない」とし、それ以前の使用量や 使用したマンション名は明らかにしていない。
入居者からの苦情を受けた大阪府が昨年5月、大京の担当者から事情を聴き、パンフ レットの表現が誤解を招きかねないと指摘。大京はパンフレットの使用をやめた。
また、いち早く健康被害を訴えた2世帯に対し、奥田一副社長が昨年4月、マンショ ンを訪れて直接謝罪し、2戸の買い戻しと移転費用などの補償を申し出た。1世帯とは 交渉が決裂したが、残る1世帯と交渉が続いている。ほかにも十数世帯がリフォームな どの補償交渉を検討している。
00年に全国で9000戸以上を販売した大京は、このマンションの入居者に対し「 より安全な建材が、この時期には供給不足で入手できなかった」と説明している。
● 教科書でCS症状悪化
教科書協会 (2003.2.23 毎日)
ヘッドライン
表紙の溶剤が原因
シックハウス症候群の重症例である化学物質過敏症(CS)などになった児童・生徒 が教科書のインキやコーティング材料で体調が悪化するとの訴えを受け、教科書協会( 事務局・東京都江東区、加盟57社)は「アレルギー問題特別委員会」を設け、調査研 究に乗り出した。既に文部科学省に対し、教科書のカラーコピーでの再製本で症状を軽 減する効果があったと報告している。協会は子どもが日常使う教科書による被害を重視 し、対応方法などを本格的に検討する。
協会によると、昨年6月以降、CSの子どもらが通学する学校の校長や教育委員会か ら「教科書のにおいでアレルギー性の症状が起きる」などと約10件の訴えが協会にあ った。
調査の結果、教科書の表紙などの影響で頭痛、腰痛、のどの痛み、筋肉のけいれんが起 きたり、情緒面で不安定になったりする子どもがいた。CSの児童の主治医は「表紙の 材料に使われている溶剤に反応している場合が多い」と説明した。
印刷や製紙の業界などは、シックハウス症候群の原因とな る化学物質のトルエンなどを教科書に使用していることは認めたが、「熱加工するので 印刷物への残留は考えられない」などと回答したという。
CSの子どもの保護者らでつくる市民団体「シックハウス連絡会」は今月、「天日干 しやコピーによる対応には限界がある」などとして教科書材料の見直しを求める要望書 を協会と文科省に提出した。
● 児童に医療費給付
調布市 (2003.2.7 共同)
ヘッドライン
調和小学校新校舎
シックハウス
東京都調布市立調和小(児童数410人)の児童の一部が、昨年 9月に新校舎に移った後、頭痛や目の痛みなどを訴えたことから、 調布市はシックハウス症候群とみて、病院で受診した児童を対象に 医療費を給付することを決め7日、保護者から申請を受け付けた。
市教委によると、症状がある児童の正確な人数は分かっていない が、3人が避難的な措置として転校している。
調和小では昨年7月、建材や接着剤に含まれ、シックハウスの原 因物質とされるホルムアルデヒドなどの化学物質が、基準値の十数 倍の値で検出され、同年8月にも2、3倍の値が出た。
数値が減少傾向にあるとの判断から新校舎に移ったが、症状を訴 える児童が出て、調布市はNPO法人「シックハウスを考える会」 (大阪府)に調査を依頼した。
同会は近く原因物質の発生源を特定する調査を行う。市は調査結 果に応じ校舎を改修する方針。
● 指針値あるのは13物質だけ
厚労省 (2003.2.2 共同)
ヘッドライン
遅れるシックハウス対策
シックハウス症候群による健康被害を防ぐため国の指針値が設定 されている化学物質は、 ホルムアルデヒドやフタル酸ジエチルヘキシル(DEHP)などわずか13種類。 1日、新たに原因物質との 疑いが浮上した2―エチル―1―ヘキサノール(2E1H)を含め 指針値がない化学物質は多く、対策強化が急務だ。
指針値は
①国の実態調査で濃度が高い
②海外で新たに規制対象となるなど早急な対応が必要
―などの基準に基づき順次設定されている。 個別の化学物質の指針値とは別に、当面実現可能な範囲で室内 空気中の化学物質総量の目標値もできた。
だが、室内空気中に存在する化学物質はすべて人の健康に何らか の影響を与える恐れがあるともいわれ、今後個別の化学物質の指針 値設定作業を大幅に加速させる必要があるのが実情だ。
厚生労働省は4月から、面積が一定規模以上の大学施設や官公庁 、オフィスビルなどを対象に、室内空気のホルムアルデヒド濃度の 法的規制値を設定し、対策を強化する。
「ホルムアルデヒドの濃度を抑えるよう換気を徹底すれば、ほか の物質の濃度も自然に低くなる」というのが厚労省の説明だ。
だが今回のケースは、ホルムアルデヒドは指針値以下なのに2E 1Hの濃度が突出して高く、同省の想定に疑問を投げ掛けるものだ 。
厚労省の担当者は「研究班による事実関係の解明を待って対応を 検討したい」と話している。
● 学生らにシックハウス症状
厚労省 (2003.2.2 共同)
ヘッドライン
校舎の空気から高濃度検出
中部地方の公立大で2001年、特定の校舎を利用している学生 と教職員計37人が頭痛やせき、目、のどの刺激感などシックハ ウス症候群とみられる症状を訴えていたことが1日、厚生労働省の 研究班の調査で分かった。
室内の空気からプラスチックや塩化ビニールに含まれるフタル酸 ジエチルヘキシル(DEHP)の分解物が高濃度で検出され、原因 物質との疑いが浮上している。この分解物と同症候群の関連を示す データは国内ではほとんどなく、国は新たな対策を迫られそうだ。
検出されたのはDEHPが水分と反応、分解して生じる2―エチ ル―1―ヘキサノール(2E1H)。
研究班は、1998年に新築された校舎を利用する教職員から2 000年12月にシックハウス症候群の訴えを受け、翌年3月に校 舎内の空気を測定。症状がひどくなる会議室で、2E1Hが空気1 立方メートル中469マイクログラム(マイクロは百万分の一 )検出された。症状が出にくいほかの部屋は85マイクログラム と低かった。
さらにアンケートの結果、この校舎を利用する教職員の約17% (9人)、学生の約4%(27人)にも同様の症状が見つかり、 最初の教職員と合わせ有症者は計37人となった。
2001年8月の測定では、症状の訴えが多いセミナー室で1086 マイクログラム、訴えが少ない廊下は164マイクログラムと10 倍以上の開きがあり、症状の頻度と相関関係がみられた。
2002年9月には会議室で最高の1183マイクログラムを記録 。厚労省が室内空気中の化学物質(揮発性有機化合物)総量の上限 目標とする400マイクログラムに対し、2E1Hだけで約3倍。セ ミナー室も565マイクログラムと依然高く、2E1Hが床か ら発生していることも判明した。
同症候群は新築の住宅や保育所、小学校などで問題となっている が、大学で多数の有症者が確認されるのは極めて異例。研究班は新 築から3―4年経ても濃度が下がらないことから、床材などに含ま れるDEHPが日常的に分解し、2E1Hが発生し続けている可能 性があるとみて発生原因の解明を急いでいる。
● 都内の小中で指針値上回る化学物質
東京都 (2003.1.24 共同)
ヘッドライン
35カ所中8施設
東京都が都内の公立の幼稚園や小、中学校など子供が使う施設35カ所の 室内空気を調べた結果、シックハウス症候群の原因とさ れるホルムアルデヒドなどの化学物質が延べ8施設で室内濃度指針 値を上回っていたことが24日、分かった。 都健康局は、昨年6月から12月にかけて、施設の室内の空気を 採取して調査。
厚生労働省の室内濃度指針値が定められている化学物質のうち、 ホルムアルデヒドが中学二校と養護学校、トルエンが小、中学各一 校、ダイアジノンが保育園、アセトアルデヒドが幼稚園と中学で、 それぞれ指針値を上回った。
小、中学校で指針値を上回ったのはすべて音楽室やコンピュータ ー室などの特別教室。都は「特別教室は一日の信用頻度が少なく、 連続して換気しないからではないか」としている。
|