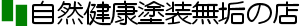サンウッド旧ニュース2
● 園児19人シックハウス症候群
大阪府堺市の保育園 (2002.8.19 毎日)
ヘッドライン
新築の園舎から12倍のトルエン
新築の園舎から国の指針値を約12倍も上回る化学物質のトルエンが検出された大阪 府堺市東湊町5丁の湊保育園で、専門医らの調査によって園児19人がシックハウス症 候群と判断された。専門医らは19日、早期の対策や他の新改築保育園での化学物質測 定を求める陳情書を堺市議会に提出する。
大阪府保険医協会のシックハウス対策室長の笹川征雄医師らが父母の協力を得て全園 児138人を対象に、シックハウス症候群かどうかを判別する問診票を配布して調査し た。134人から回答があり、そのうち37人に「目がしょぼしょぼする」「目やにが 出る」といった症状があった。 笹川医師らは、発症時期や、退園後に改善したかどうかも考慮して症例を絞り込んだ 結果、シックハウス症候群である可能性が「極めて高い」園児は14人、「高い」園児 は5人と判断した。 笹川医師は「小児は環境への抵抗力や対応能力が弱いので、真剣に受け止めるべきだ 」と話している。
同園では現在、施工業者が、NPO「シックハウスを考える会」(大阪府四条畷市) の現場調査や研究による助言を受けて改装を計画している。 堺市では昨年、市立五ケ荘保育所でも園児と保育士計26人にシックハウス症候群が 出て、今年5月に保育士4人が全国初の労災認定を受けた。
● シックハウス症候群、労災申請
大阪・吹田市図書館職員 (2002.8.14 毎日)
ヘッドライン
公民館で改装直後
大阪府吹田市の市立図書館北千里分室・北千里地区公民館で改装直後に職員や利用者 にシックハウス症候群とみられる症状が出た問題で、女性職員4人の症状が悪化し、化 学物質過敏症(CS)と診断されていたことが14日、分かった。4人とも労災(公務 災害)認定を請求した。CSは多種類の化学物質に対し、ごく微量でも反応するもので 、4人は2~3カ月間、勤務を休む見通しという。
市教委によると、4人は4月の発症後、数日間休むなどした後、出勤したが、再び症 状が悪化した。7月にCSで自宅療養が必要と診断され、現在休業している。
吹田市職員労働組合によると、4人のうちの1人は微量の化学物質に反応し、改装し たデパートなどへも近寄れず、印刷物のインキにも反応してせきが止まらなくなる状態 という。
また、別の男性職員1人もCSの疑いがあると診断された。さらに応援で代わりに配 置された職員も一時、目がちかちかし、風邪のような症状を訴えたという。
この施設では、厚生労働省の指針値の5倍に当たるトルエンが検出されたが、現在は 指針値を下回っている。しかし、4人の診断ではポリウレタン系の塗料や接着剤に使わ れる化学物質のイソシアネート中毒の疑いがあるという。イソシアネートは、ぜんそく や皮膚炎などの症状があらわれるとされる。
● シックハウス症候群で労災認定
天満労働基準監督署 (2002.8.6 毎日)
ヘッドライン
民間施設で初
大阪市北区の改装工事後の民間オフィスで、シックハウス症候群にかかったと訴えて いた家庭雑貨卸会社の女性契約社員、花沢裕美子さん(38)=大阪府箕面市=の労災 保険請求に対し、天満労働基準監督署(大阪市北区)は5日までに、労災認定した。民 間施設をめぐる初の認定事例とみられる。これをきっかけにシックハウスへの労災認定 事例が増える可能性がある。
花沢さんはオフィスの改装後の一昨年5月、吐き気や頭痛を覚えるなどホルムアルデ ヒド中毒の症状が出た。その後は微量の化学物質で体が不調になる化学物質過敏症にな り、7月も自宅近くの家屋の改装で体がけいれんしたという。今回、発症時から約2年 間の治療費と休業補償の給付請求すべてが認められた。 厚生労働省によると、同様の事例では、今年5月に大阪府堺市立保育所の仮園舎でア ルバイト4人が認定された事例があるが、民間の施設では報告はない。
● 12月に過敏症の実態調査
文科省 (2002.8.5 共同)
ヘッドライン
シックハウス対策
子どもが一日の大半を過ごす学校で、ごく微量の化学物質にも反 応するシックハウス症候群の過敏症について、文部科学省は五日、 実態把握のための調査研究手法を検討する第一回の会議を開いた。 会議には公衆衛生や建築学の専門家や教育委員会の担当者らが出 席。「新しい机からも相当な量の化学物質が出ている。学校に特有 の備品を考えに入れて調査すべきだ」「保護者の不安感が強く、そ れが子どもにもうつってどんどん消極的になっていく」などの意見や 問題点が出された。
文科省は実態把握のための調査内容や方法を検討し、十二月をめ どに調査を実施する方針。また学校現場でもできる簡単な濃度測定 方法などについても検討する。 シックハウス症候群は、新築や改築をした建物から発生する化学 物質などで目や鼻の刺激症状や吐き気を引き起こし、日常生活に著 しく支障を来すケースもある。 厚生労働省はホルムアルデヒドなど十三の化学物質について室内 濃度の指針値を定めているが、指針値を下回る濃度でも反応してし まう過敏症には定義や診断基準がなく、調査方法も確立していない。
● 化学物質を取り除く吸着剤
松下電器産業 (2002.8.2 共同)
ヘッドライン
再利用も可能
松下電器産業は2日、悪臭やシックハウス症候群の原因となる化 学物質を取り除く吸着剤を開発したと発表した。10月にサンプル 出荷を始め、し尿処理などの需要を見込んでいる。
同社の従来型より5倍寿命が長く、再利用も可能だという。加工 しやすいため、脱臭機や空気清浄機、介護用シーツなどへの用途を 検討している。
● 環境配慮の床ワックス発売
イケダコ (2002.8.1 共同)
ヘッドライン
独リボス社のグラノス
環境に配慮した商品を扱っているイケダコーポレーション(大阪 市)は、リボス社(ドイツ)*の木床・家具用ワックス「グラノス」 を1日に発売した。合成界面活性剤や有機溶剤を使用せず、植物成 分を主に配合してシックハウス症候群に配慮。汚れ落としも同時に できる。250ミリリットル入りで1600円。
* 弊社の塗装はリボス社の塗料を採用しています。
● 2化学物質を初めて法規制
衆院 (2002.7.5)
ヘッドライン
ホルムアルデヒドとクロルピリホス
建材などに含まれる化学物質による室内空気汚染で体調を壊すシックハウス症候群対 策として、2種類の化学物質の使用を禁止・制限する建築基準法や都市計画法などの一 括改正法が5日の衆院本会議で、自民、民主などの賛成多数で可決され成立した。同症 候群の原因物質が法規制されるのは初めて。1年以内に施行される。
規制されるのは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスと、合板や壁紙の接 着剤などから出るホルムアルデヒドの2種類。それぞれの物質を出す恐れのある建材の うち、クロルピリホスは使用禁止、ホルムアルデヒドは一定面積以上の使用を制限する 。また、マンションなど気密性の高い住宅では換気設備の設置を義務づける。違反する と、建築業者などに自治体から改修命令が出され、従わない場合には1年以下の懲役か 50万円以下の罰金が科されることがある。
室内汚染にかかわるものとして、厚生労働省は13種類の化学物質を選んで室内濃度 の指針値を定めている。国土交通省などの調査の結果、クロルピリホス(指針値0.0 7ppb)、ホルムアルデヒド(同0.08ppm)ともに指針値を上回る住宅が見つ かり、発生源が特定できたため規制することにした。とくにクロルピリホスはいったん 発散すると換気しても効果がないため、使用禁止にしたという。
国土交通省の社会資本整備審議会は、トルエン(指針値0.07ppm)、キシレン (同0.20ppm)などについても規制を検討すべきだとしている。同省ではこれら の物質についても指針値を上回る事例が見つかり、発生源が特定でき次第、順次規制対 象に加えることにしている。
都市計画法の改正では、NPO(非営利組織)やまちづくり協議会、土地所有者など の民間団体が自治体に対し都市計画の提案ができる制度が創設される。 開発が規制される都市計画区域のうち一定規模以上の区域について、3分の2以上の 地主の同意を条件にまちづくり案を提案できるようにする。自治体は民間案をベースに 別途、案をつくって都市計画審議会に諮る。その際、民間案もあわせて審議会に提出す る。不採用の場合には、提案者に理由を通知しなければならない。
今回、規制対象となるのは2物質のみだが、国土交通省住宅局建築指導課は「規制に必要 な研究結果が整い次第、規制物質を増やす」としている。 健康被害との関連が懸念される化学物質については、厚生労働省が1997年以降、 これまでホルムアルデヒド、クロルピリホスを含む13物質について室内濃度のガイ ドラインを設けており、今回の規制はこの目安を守るための手だて。 室内空気と健康の問題に詳しい柳沢幸雄東大教授は「建物完成後の濃度測定の義務 がなく、実効性には課題もあるが、化学物質規制を強制力のある建築基準法に明文化 したことの意義は大きい」と話している。
● シックハウスで初の法規制
衆院 (2002.6.28 共同)
ヘッドライン
建築基準法改正案を可決
衆院国土交通委員会は二十八日、住宅建材などに使用される化学 物質で、吐き気などの健康被害を引き起こすシックハウス症候群の 原因物質の規制を盛り込んだ建築基準法改正案を与党三党などの賛 成多数で可決した。
シックハウスに対する本格的な法的規制は初めて。早ければ、七 月二日の衆院本会議で可決、成立する見通しで、公布から一年以内 に施行される。
法案では、合板の木質建材などに使われる刺激臭のあるホルムア ルデヒドの使用を制限。JIS(日本工業規格)などで、放出量を 明示した等級の建材の使用面積を制限し、等級区分のない建材の使 用は禁止する。
また建材以外にも家具からホルムアルデヒドが発散する恐れがあ るため、居室に換気設備の設置も義務付けた。
● 指針値5倍以上のトルエン
大阪府吹田市 (2002.6.27 毎日)
ヘッドライン
同市都市整備部建築課が伝えず
大阪府吹田市の市立図書館北千里分室兼北千里地区公民館で、職員や利用者十数人が シックハウス症候群とみられる体の不調を訴えた問題で、改装を担当した同市都市整備 部建築課が、厚生労働省の指針値の5倍以上のトルエンが改装直後の今年3月に検出さ れたのを知っていながら、公民館・図書館運営を担当する同市教委の社会教育部に3カ 月近く伝えていなかったことが26日、分かった。この間に、被害が出ていた。
建築課は「トルエンはやがて減ると思い、情報を抱え込んでしまった」と弁明、故意 に隠したのではないことを強調しているが、批判が高まっている。
建築課の説明によると、今年3月29日、シックハウス症候群の原因物質であるトル エンが公民館で指針値の3・8倍、図書館分室で5・4倍検出されたことを、工事業者 から報告された。ところが、トルエンとともにシックハウス症候群の原因物質とされて いるホルムアルデヒドは指針値を上回らなかったことから事態を軽視し、社会教育部に 伝えずに「最終検査は済んだ」として施設の引き渡しをしたという。4月3日の新装開 館直後から職員5人が目やのどなど体の不調を訴え始めた。
社会教育部は今月17日、毎日新聞の取材に、「改装時に化学物質の測定をしたが問 題なかった」などと説明。建築課から何も言ってこなかったので、大丈夫と思っていた との見解だった。今月24日にトルエンの検出結果を初めて知らされたという。
斎藤欣夫・社会教育部次長は「データを見てびっくりした。早く知らされていれば、 換気などの対策をしていただろう」と話している。
NPO法人「シックハウスを考える会」の上原裕之理事長の話トルエン濃度はなか なか下がらないことは、国の報告にもある。住民の生命と財産を守るのが公務員なら、 すぐに専門の機関に相談して原因を調査し、物質の除去や密封などの対策をするべきだ った。
● 化学物質の測定を義務化
厚労省 (2002.6.25 共同)
ヘッドライン
ホルムアルデヒドの測定を義務付け
新築の建物で発生するシックハウス症候群が社会問題となる中、 厚生労働省は二十四日までに、学校やホテル、百貨店の新築時や大 規模な改修時に、原因の一つとされる化学物質ホルムアルデヒドの 測定を義務付ける方針を決めた。 違反すれば都道府県などが改善命令を出し、従わなければ建物の 使用を中止させる「罰則」も適用される。 ビルの配管内で繁殖し、感染すれば肺炎を引き起こすレジオネラ 菌による健康被害を防ぐため、飲料用や手洗い、シャワーの給湯設 備向け衛生管理基準も新設。九月にもビル衛生管理法の関連政令と 省令を、一九七○年の同法制定以来三十二年ぶりに抜本的に改正す る。
厚労省によると、新築されたばかりの学校や改修された図書館で 健康被害を訴えるケースが相次いでいるのを受け、建物の新築や大 規模な改修の際、使用前に室内空気中のホルムアルデヒド濃度を測 定させ、国の指針値(○・○八PPm)を上回るような場合、改善 策を取らせる。
トルエンなどシックハウス症候群との関連が指摘される化学物質 はほかにもあるが、建材や家具に最も広く使われていることから、 今回はホルムアルデヒドだけに絞った。
測定の対象となるのは、ビル衛生管理法で「特定建築物」になっ ている面積が一定以上の学校や百貨店、ホテルのほか映画館、会社 事務所、旅館など。二○○○年度末時点で全国の約三万四千施設。 レジオネラ菌対策として既に、ビル衛生管理法に基づき空調設備 の衛生管理基準が定められている。しかし給湯設備には法的な基準 がなく、管理者の自主的な対応に委ねられていた。
政、省令改正は、旧厚生省が九九年にまとめたレジオネラ症防止 指針を踏まえ、レジオネラ菌除去に必要な清掃、消毒の方法や回数 などの基準を定める。
厚労省の担当者は「これらの対策が確実に実行されるように監視 の強化を各自治体に求めたい」としている。
市民団体「化学物質過敏症患者の会」の海老原節子代表は「測定 の対象物質を増やしたり、一般住宅の引き渡しの際に測定を義務付 けたりしてほしい。早急に被害をなくす対策を進めるべきだ」と指 摘しており、今後の取り組みが注目される。
シックハウス症候群によるとみられる健康被害は、最近では高知 県内の公立中学校や大阪府内の図書館で表面化。大阪府内の保育所 の女性保育士四人にシックハウス症候群による労災が認められたケ ースもある。
ホルムアルデヒドの指針値は旧厚生省が九七年に策定。現在、指 針値が定められている対象物質はこれを含め計十三種類。 厚労省の担当者は「今後、ホルムアルデヒド以外の化学物質も測 定対象に加えるか、データを集め検討したい」としている。